 | ||
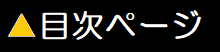 |
||
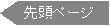 |
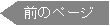 |
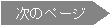 |
橋の終わりがようやく見えました。40〜50mくらいあったでしょうか。 |

|
|
再び針葉樹林の道になります。 |

|
|
突然前方に建物が現れ、何とこの道はその中に入って行きます。 |

|
|
無人のその小屋の中には土の窯がありました。炭焼き窯なのか陶芸用の窯なのかわかりませんが、小屋の外に大量に積み上げられた丸太の切り口の新しさからすると今でも使われているように思えます。 |

|
|
小屋から右側にも道らしきものが続いているので行ってみました。 |

|
|
途中、送電線点検用の道が分岐していたのを思い出し、その地点まで戻ってみました。 |

|
|
一旦元の地点に戻って自転車と荷物を担いで再び急斜面を登り、尾根に出ました。 |

|
|
ハッキリした道ですがやはり倒木などでほとんど押し歩き。 |

|
|
荒れた塹壕状の道を登りつめると、 |

|
|
前方が開けススキの原に出ました。 |

|
|
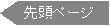 |
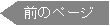 |
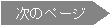 |
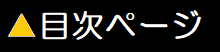 |
||
 | ||